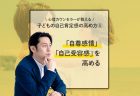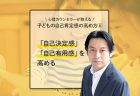日本における「自己肯定感」ブームを作った第一人者であるカリスマ心理カウンセラーの中島輝さんが、自己肯定感の重要性と自己肯定感を高める方法を解説してくれる連載「【心理カウンセラーが教える】子どもの自己肯定感の高め方」。第5回目は、中島さんが自己肯定感を構成する要素だと考える「6つの感」のうち、「自己効力感」「自己信頼感」を取り上げます。
構成/岩川悟(合同会社スリップストリーム)
取材・文/清家茂樹 写真/川しまゆうこ
「自分にはできる」と思える感覚――自己効力感

「ありのままの自分を肯定し、認めることができる感覚」を指すのが、「自己肯定感」です。この自己肯定感はいくつかの要素で構成されており、その要素とはわたしが「6つの感」と呼ぶものです。自己肯定感を1本の「木」にたとえると、それぞれが根や幹、枝、葉などにあたります。
「6つの感」のうち、今回は「自己効力感」と「自己信頼感」について解説していきましょう。
自己効力感とは、「自分にはできると思える感覚」のこと。なんらかのチャレンジをしようというときに、「どうせ自分にはできないだろう…」と思うのか、それとも「きっと自分にはできる!」と思うのか、そのちがいによって人生は大きく変わります。
前者の場合、チャレンジする前からあきらめているような状態ですから、そのチャレンジが成功する可能性は限りなくゼロに近づきます。もし成功するとしたら、それはただの偶然によるものでしょう。
一方、後者の場合は、「きっと自分にはできる!」と自分の力を信じているために、チャレンジする際も持てる以上の力を発揮することができます。結果として、そのチャレンジが成功する可能性も高まるでしょう。
自己効力感が育てば、何度でもチャレンジできる

もちろん、たとえ「きっと自分にはできる!」と自分の力を信じていたとしても、そのチャレンジが失敗に終わることもあります。けれども、自己効力感が高まっていて自分の可能性を信じられている人は、そこで終わりません。
失敗などなんらかの問題に直面したときにも、「だったら、今度はこうすればきっとうまくいくはずだ!」とプランを立て、立ち止まることなく前進する勇気やチャレンジ精神を持つことができるのです。
このように、自己効力感が高まっていれば、何度でもチャレンジする力を得られ、「人生はいつからでも再起可能だ!」と信じることができます。
こうした特性から、自己肯定感を1本の「木」だとすると、この自己効力感はしなやかな「枝」にあたるとわたしは考えています。幹からたくさんの枝が伸びていくように、あるいは折れても折れても新しい枝が出てくるように、どんな困難が待ち受けていようとも、自分の人生を自分の力で絶えず歩み続ける力を自己効力感が与えてくれるのです。
終身雇用制で守られ、「いい企業に就職すれば一生安泰」という時代はとっくに終わりました。これからの変化が激しく厳しい時代を生き抜いていかなければならない子どもたちには、どんな局面に置かれても「きっと自分にはできる!」と前を向いて進んでいける勇気が大きな支えとなってくれるはずです。
自分を信じられる感覚――自己信頼感

続いて解説する自己信頼感については、その字面からすぐにイメージできるでしょう。「自分を信じられる感覚」のことで、光合成によって養分を与えてくれる木にとっての「葉」のように、人生を豊かにする養分となってくれます。
自己信頼感が高まっている人は、いついかなるときも自分に自信を持ち、自分のいまと未来の可能性を信じて行動を続けることができます。いわゆる「非認知能力」のひとつとされる「やり抜く力」とも大いに関連する感覚です。
わたしが尊敬しているアメリカの思想家、ラルフ・ウォルドー・エマソンはこんな言葉を残しています。
「根拠のない自信こそが絶対的な自信である」
では、逆に「根拠のある自信」しかない人のケースを考えてみましょう。たとえば、自分の肩書というものを根拠として自信を持っている人の場合、立場を追われてその肩書を失えば自信の根拠が消えます。結果として自信を失い、行動を続ける力まで失ってしまうでしょう。
エマソンが伝えたかったのは、「自分を信じ抜くことでどんな困難な状況でも人生を切り開いていくことができる」というメッセージだとわたしは思っています。
また、自己信頼感によって根拠のない自信を持てていれば、自分を信じられているために行動の幅が広がり、自分の世界を大きく広げてくれる「積極性」を手に入れることにもつながるでしょう。
わたしたち日本人は、世界的に見てとても「謙虚」な民族だといわれます。もちろん、謙虚さにもよい面はたくさんあります。しかし、急速にグローバル化が進んでいるこれからの社会で優秀な外国人たちに負けず自分の力をしっかり発揮するには、積極性も大きな武器のひとつになると思います。
ネガティブな言葉をポジティブにとらえ直す「リフレーミング」
では、自己効力感と自己信頼感を高めるためのワークを紹介します。そのワークとは、「リフレーミング」というものです。
自己効力感を高めて「きっと自分にはできる!」と思えるようになるには、あるいは自己信頼感を高めていついかなるときも自分を信じられるようになるには、たとえ自分にネガティブな部分があったとしても、それをポジティブな部分としてとらえることが鍵となります。そうするためのワークが「リフレーミング」です。
◆ワーク【リフレーミング】
リフレーミングとは、「ものごとをとらえるフレーム(枠)を変える」というもので、具体的には、「ネガティブにとらえたものを、ポジティブにとらえ直す」ことです。
自己効力感や自己信頼感が低下しているときは、どうしてもものごとのネガティブな側面ばかりに目が向き、ネガティブな考えが浮かんだりネガティブな言葉を発したりしがちです。そのときに、あえてポジティブな考えや言葉に変換するのです。そうすることで、自分の頭にどんどんポジティブな言葉を投げかけ、思考そのものをポジティブな方向に導くことで自己効力感と自己信頼感を高めることができます。
たとえば、大きな仕事を前にしたときに、つい「失敗しちゃ駄目だぞ…」と思ってしまったとします。それでは、わざわざ自分を緊張させているようなもの。結果として自己効力感と自己信頼感は低下してしまい、逆に失敗する可能性が高まってしまいます。そうではなく、「成功するぞ!」というふうに思い直すのです。
以下に、わたしからリフレーミングの例をいくつか挙げておきます。これらを参考に、ポジティブな言葉を自分のなかにどんどん増やしていきましょう。
【リフレーミングの例】
| ネガティブな言葉 | ポジティブな言葉 |
|---|---|
| 疲れた | よく頑張った |
| できない | やってみよう |
| どうせ無理 | なんとかなる |
| 嫌だなあ | ○○だといいなあ |
| すみません | ありがとう |
| 失敗しないように | 成功するように |
| つまらない | 面白いかも |
| 面倒くさい | ま、いっか |
ただ、これを子どもたち自身が行うことはちょっと難しいかもしれません。そこで、保育士さんたちには、子どもたちがネガティブな言葉を発したときに、その言葉を受け止めたうえでポジティブな声かけをしてあげてほしいのです。たとえば、こんな具合です。
子ども「最近、雨ばっかりで嫌だなあ…」
保育士「そうだね。でも、きっとカエルさんはよろこんでるよ」
こういうことの積み重ねで、ネガティブな部分にばかり目が向いていた子どもの視点が大きく変わり、ものごとや自分のポジティブな側面をとらえることができるようになっていくと思います。
【自己肯定感を高めるワークを行う際の留意点】
・大人にも子どもにも効果があるため、保育士と子ども、あるいは親子で一緒に楽しむ
・子どもがやりたがらないワークは、無理にやらせない
・保育士や親が楽しんで取り組んでいる姿を子どもに見せる
Jリーガー、上場企業の経営者など1万5000名以上のメンターを務める。現在は「自己肯定感の重要性をすべての人に伝え、自立した生き方を推奨する」ことを掲げ、「肯定心理学協会」や 新しい生き方を探求する「輝塾」の運営のほか、広く中島流メンタル・メソッドを知ってもらうための「自己肯定感カウンセラー講座」「自己肯定感ノート講座」「自己肯定感コーチング講座」などを主催。著書に『自己肯定感の教科書』『自己肯定感ノート』(SBクリエイティブ)、『習慣化は自己肯定感が10割』(学研プラス)など多数。
自己肯定感アカデミー(https://ac-jikokoutei.com/)